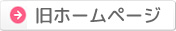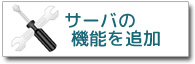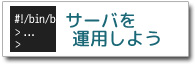玄箱をファイルサーバとして使用している場合、そのデータのバックアップも必要になってくるかもしれません。
玄箱のHDDが壊れてしまった時、すぐにデータのリストアが出来るようにミラーリングをするのがよいでしょう。

このサイトの方法でsqueeze化した玄箱にUSBを差し込めばそのまま認識してくれるでしょう。もしも玄箱のDebianバージョンがそれよりも古い方法でセットアップしたのであれば認識しない場合があります。その場合はカーネルの再構築を行なってUSB機器が認識するようにする必要があります。その方法は私の旧ページに記載していますので御覧ください。
玄箱にUSBを差し込んだら下記のコマンド入力をして認識しているかどうか確認します。結果にそれらしいものが書かれていればOKです。(usb-storageとかsda1とか)

玄箱用に記録媒体をフォーマットします(ext3形式)
ext3でフォーマットされたストレージを下記のコマンドでマウントして実際にデータの書き込みが出来る状態にします。
先ずはマウントする場所を作成します。名前はなんでもいいです。
マウントコマンド。ファイルシステムは自動で認識されます
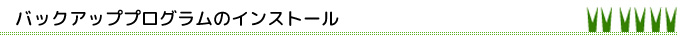
rsync:このパッケージは差分バックアップが出来るのが特徴。最初にフルバックアップを取った後は 変更されたファイルだけをバックアップしてくれるので効率的にデータの同期がとれます
コマンド:バックアップの実行
マウントした記録媒体にディレクトリを作製してそこにバックアップしてみます。
例えば、設定データの入っている「/etc」ディレクトリを丸ごとバックアップを開始します。「--delete」オプションを追加してコマンド入力すれば、元データを削除した場合、バックアップ先のデータも同期して削除してくれます。
※ここで大事なのはバックアップデータのあるディレクトリの表記ですが、 「/etc」の様にディレクトリの最後に「/」をつけない場合、まず「etc」ディレクトリが作成されてから 中のディレクトリやデータがコピーされていきます。つまりバックアップ先は「/mnt/usb/backup/etc/データ」となってしまいます。
最初のバックアップは時間がかかりますが2回目以降は変更のあったデータだけコピーするので 時間はかからないはずです。ちなみに、私は150G近いデータをバックアップするのに10時間くらいかかりました。

バックアップしたくないデータは除外オプション(--exclude)を追加してコマンド入力します。

先ずはrsyncによるバックアップをするスクリプトを作成します。その後、Cronに登録してバックアップ自動化する。
ファイルを新規作成(どこでもいい)して下記の文章を入力する
内容は1.外付け記録媒体をマウントする。2.rsyncコマンドでバックアップを取る。3.マウントを解除する
PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin
mount /dev/sda /mnt/usb 認識されるデバイス名に注意。USBを差し込む順番によって違ってきます (/dev/sda,/dev/sdb・・・)
rsync -av --delete /etc/ /mnt/usb/backup
umount /mnt/usb
シェルスクリプトに実行権限を与えます。
Cronに登録して夜中の3時にバックアップを開始する
これで自動バックアップが出来ますが、常に外付記録媒体の電源を入れておく必要は無く、バックアップを取りたい日だけ電源を入れておき、夜中の 3時にバックアップが開始されて朝になったら外付記録媒体の電源を切れば電気代がもったいなくありません。
もしも外付記録媒体の電源が入っていない状態で夜中の3時になってもマウント出来ないところでコマンドは終了してしまいます。
しかし、この方法で注意することは、外付記録媒体の電源を入れてマウントされる時に認識されるデバイス名が違っているとそこでもコマンドは終了してしまいます。(sdaじゃなくてsdbとか)
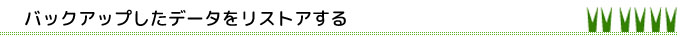
バックアップしたデータをリストアするにはコピー元とコピー先を逆転させればOKです。
 | Linux逆引き大全555の極意 コマンド編 伊藤 幸夫    ![Linuxエンジニア養成読本 [仕事で使うための必須知識&ノウハウ満載!] (Software Design plus)](http://images.amazon.com/images/P/4774146013.09._SCTHUMBZZZ_.jpg)  by G-Tools |